限度額適用認定証の役割
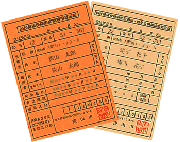
国民健康保険に加入している方は、保険年金課(市役所1階)に申請することにより「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
また、認定証の有効期限は原則、毎年7月31日です。8月以降も毎月の医療費が高額になる方は更新の手続きをお願いします。
- 認定証を資格確認書等と一緒に医療機関の窓口に提示することにより、1か月ごとの医療費が高額になった場合でも、支払う金額が世帯毎の自己負担限度額までとなります。
- 住民税非課税世帯の方は、食事代もあわせて減額となります。
- 70歳から74歳の方については、高齢受給者証2割負担の住民税課税世帯の方及び、高齢受給者証3割負担かつ住民税課税所得が690万円以上の方は高齢受給者証が認定証の代わりになりますので申請の必要はありません。
申請方法
下記の書類を持参し、保険年金課(市役所1階)で手続きをしてください。
また、来庁が難しい場合は事前に保険年金課へご相談ください。国民健康保険税の納付状況や収入の申告状況を確認させていただいた上で、郵送申請のご案内が可能な場合があります。
※災害など特別な事情以外で、国民健康保険税を滞納している世帯には交付できない場合があります。
※世帯主(国保未加入者含む)や国保加入者で申告していない方がいると交付できない場合があります。
申請に必要なもの |
|
|---|
この認定証を持たずに高額な医療費を支払った場合は、後日、保険年金課(市役所1階)に申請することにより、自己負担限度額を超えた分を支給します。(該当される方は「国民健康保険高額療養費支給申請書」にてお知らせします。)
入院したときの食事代(食事療養標準負担額)
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食分として定められた標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
2025年4月1日から入院時食事代の標準負担額が変わります。
| 所得区分 | 2025年3月まで | 2025年4月から |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯 | 490円※ | 510円※ |
住民税非課税世帯 |
230円:過去12か月の入院日数が90日まで |
240円:過去12か月の入院日数が90日まで |
| 70歳以上で低所得者1に該当する人 | 110円 | 110円 |
※一部300円(2025年3月までは280円)の場合があります
- 入院時食事代の標準負担額は、高額療養費の対象にはなりません。
- 住民税非課税世帯、低所得者1または2の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。認定証がない場合、入院時食事代の標準負担額は住民税課税世帯の方と同額となりますので、入院される場合は、保険年金課(市役所1階)でお手続きをしてください。
- 低所得2とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税の方です。
- 低所得1とは、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない方です。
- 入院日数が過去12か月で90日を超える方には、長期入院該当認定をおこなう場合があります。該当する方は入院期間のわかる領収書等を保険年金課(市役所1階)へご持参ください。
住民税非課税世帯の方が何らかの理由により、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口で提示できず、住民税課税世帯の標準負担額を支払った場合は、やむを得ない事情があれば、申請により差額分の支給を受けることができます。
また、長期入院該当認定を受けた方で、91日目以降の入院で90日以内の標準負担額を支払った場合も、申請により差額分が支給されます。ただし、長期入院該当による差額の支給ができるのは、長期入院該当認定を行った月以降の分のみとなります。それ以前の月の差額は、申請が遅れたことについてやむを得ない事情がある場合を除いて支給できません。
食事代の差額申請に必要なもの |
|
|---|
療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食事と居住費として、定められた標準負担額を自己負担します。
2025年4月1日から食費の標準負担額が変わります。
| 食費・居住費の標準負担額 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯(下記以外の人) | 510円※ | 370円 |
| 住民税非課税世帯 | 240円 | 370円 |
| 低所得者2 | 240円 | 370円 |
| 低所得者1 | 140円 | 370円 |
| 食費・居住費の標準負担額 | 食費(1食当たり) | 居住費(1日当たり) |
|---|---|---|
| 住民税課税世帯(下記以外の人) | 490円※ | 370円 |
| 住民税非課税世帯 | 230円 | 370円 |
| 低所得者2 | 230円 | 370円 |
| 低所得者1 | 140円 | 370円 |
※一部医療機関では470円(2025年3月までは450円)
- 入院医療の必要性の高い状態が継続する人や回復期リハビリテーション病棟に入院している人については、上記の「入院したときの食事代の標準負担額」と同等の食材料費相当を負担します。
- 指定難病の方、老成福祉年金受給者、境界層該当者の居住費は0円です。
- 低所得2とは、同一世帯の世帯主と国民健康保険加入者が住民税非課税の人。
- 低所得1とは、住民税非課税の世帯で、世帯員の所得が一定基準に満たない人。
マイナンバーカードが限度額適用認定証として利用できます!!
マイナポータルでご自身の特定健診結果や、医療費・薬剤情報などが確認できるなど、マイナンバーカードのメリットが広がっていきます。
マイナンバーカードを限度額適用認定証として利用するためには、マイナポータル等で利用申込みが必要です。詳しくは下記をご覧ください。
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 保険年金課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2941-5174
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

