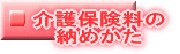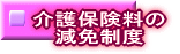2025年度(令和7年度)保険料額の算定
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、お住まいの市町村によって異なります。
狭山市では、介護サービスの利用実績や調査から把握されたサービスの利用傾向などの情報から必要となるサービスの利用量と給付費の額を見込んだ結果、第9期狭山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画の事業期間である2024年度から2026年度における保険料基準額を決定しました。
保険料基準額は3年ごとに見直しており、2024年度からの新たな基準額は、月額5,625円となっています。
なお、保険料は各年4月1日時点における住民票の世帯構成を基準として、下記の表にある所得要件等により算定しています。
【参考】第8期計画(2021年度から2023年度まで)との比較
要介護認定者の増加に伴うサービス利用の増加、施設の整備、介護報酬の改定等を受け、第9期計画における基準額月額を5,625円に定めたことにより、第8期計画の基準額月額4,784円と比較して、841円の増額となりました。
保険料 |
対象者(所得要件等) | 保険料率 | 保険料額 |
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護の受給者、または老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税 | 基準額×0.285 | 19,200円 |
| 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80.9万円以下 | |||
| 第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額80.9万円を超え120万円以下 | 基準額×0.485 | 32,700円 |
| 第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が年額120万円を超える | 基準額×0.685 | 46,200円 |
| 第4段階 | 世帯に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下 | 基準額×0.90 | 60,700円 |
| 第5段階 | 世帯に住民税課税者がおり、本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超える | 基準額 | 67,500円 |
| 第6段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円未満 | 基準額×1.20 | 81,000円 |
| 第7段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が125万円以上210万円未満 | 基準額×1.30 | 87,700円 |
| 第8段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上500万円未満 | 基準額×1.50 | 101,200円 |
| 第9段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満 | 基準額×1.70 | 114,700円 |
| 第10段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満 | 基準額×1.90 | 128,200円 |
| 第11段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,200万円未満 | 基準額×2.10 | 141,700円 |
| 第12段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,200万円以上1,500万円未満 | 基準額×2.30 | 155,200円 |
| 第13段階 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上 | 基準額×2.40 | 162,000円 |
※年額は、基準額に保険料率(割合)を乗じた額から100円未満を切り捨てた額となります
※年度の途中で65歳になられた方は、65歳をむかえる誕生日の月(誕生日が1日の場合は前月)から年度末までの月数で計算します
用語の解説
- 合計所得金額(※2024年度以降を対象とした説明です)
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
第1から5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除した金額を用いるほか、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
- 課税年金収入額
国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。
障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
- 老齢福祉年金
1911年(明治44年)4月1日以前に生まれた人などのうち、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
介護保険料額の算定例
例1
夫婦2人世帯で、夫が住民税非課税(年金収入額100万円)、妻が住民税非課税(年金収入額60万円)の場合
→夫は第2段階(32,700円)、妻が第1段階(19,200円)の保険料となります。
例2
夫婦2人世帯で、夫が住民税課税(合計所得金額120万円)、妻が住民税非課税(年金収入額60万円)の場合
→夫は第6段階(81,000円)、妻が第4段階(60,700円)の保険料となります。
例3
70歳の母と40歳の子の2人世帯で、母が住民税非課税(年金収入額90万円)、子が住民税課税の場合
→母は第5段階(67,500円)の保険料となります。
介護保険料の納めかたは下記のバナーをクリックしてください
介護保険料の減免制度は下記のバナーをクリックしてください
このページに関するお問い合わせは
健康推進部 介護保険課
電話:04-2941-4892
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。