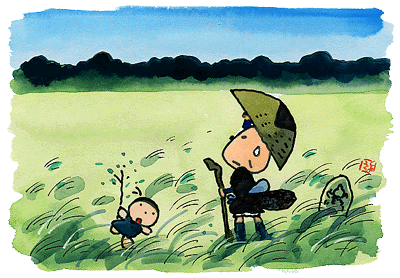
入間地区の水野という所に『逃水』という地名が今ものこっています。むかしこのあたりは、一面の荒野で入間川から遠くはなれていましたので、たいへん水にこまっていた所でした。
水があまりに少ないため、一日の畑仕事が終わって家に帰った時などは、青草を刈ってそのたばで足をふいたり、お米のとぎ汁を集めておふろにしたり、それはもう大変水に不自由していました。
そのため、このあたりには七曲りの井や堀兼の井のような深い井戸が今もなおのこっています。
これは、むかしむかし所沢のことを『とろろ沢』といったころのおはなしです。
ある日旅人が、とろろ沢の方へ行くために、この地を通りかかりました。その日は、とても暑い日でしたので、旅人は、もうのどがかわいてしかたがありませんでした。
ところが旅人は、あいにく水いれを持ちあわせていなかったとみえて、あたりに水がないものかと、キョロキョロと見まわしました。
すると、林の手前に水の流れが見つかりました。「やれよかった」よろこんだ旅人は、水にむかっていちもくさんにかけだしました。
するとどうでしょう。さっき見た所に水はなく、どんどん遠くにはなれていきます。いくらおいかけても水は遠くにいってしまいます。
それでも旅人は、水がのみたい一心で、フラフラになりながらも水の方へ走っていきました。
そして、この話がパッとひろがり、いつのまにか、この地が『逃水の里』といわれるようになりました。
逃水の原因には、蒸気説やかげろう説、そしてシンキロウ説などがありますが、武蔵野の逃水として有名になり、古歌にもしばしば歌われています。
このページに関するお問い合わせは
企画財政部 広報課
狭山市入間川1丁目23番5号
電話:04-2935-3765
FAX:04-2954-6262
この情報は役に立ちましたか?
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。

